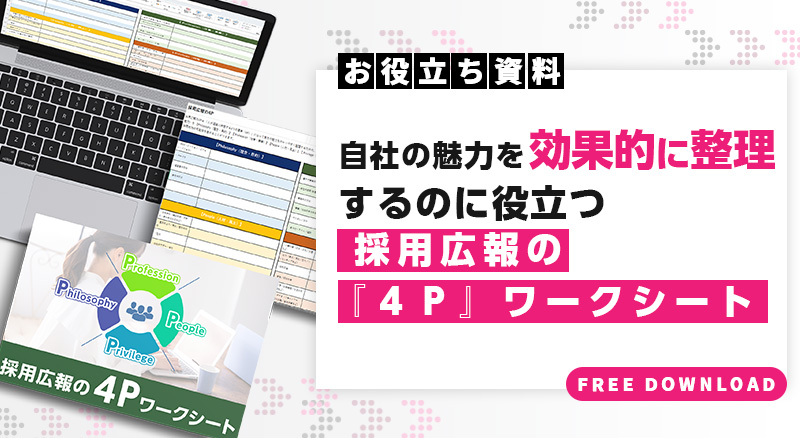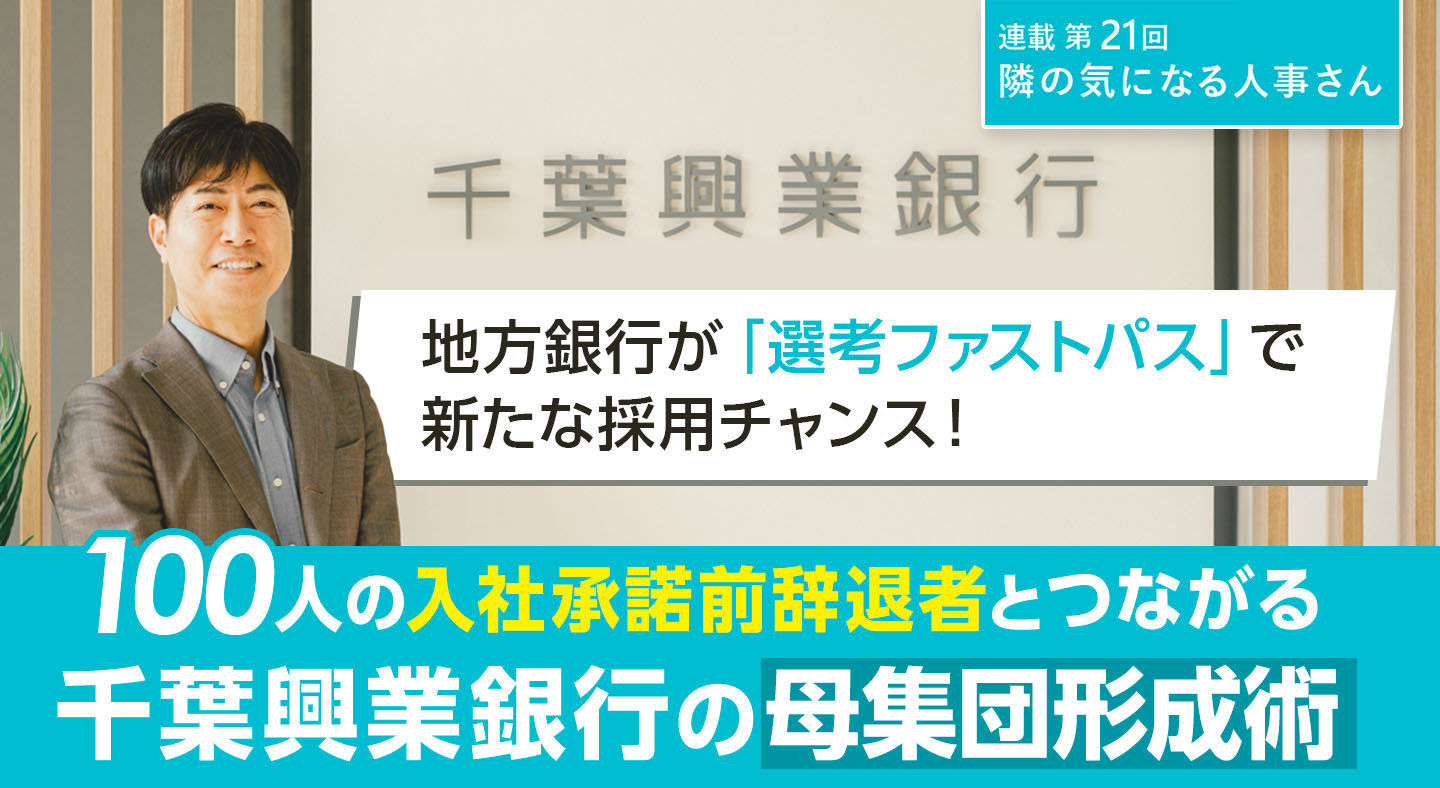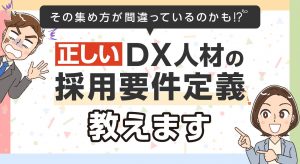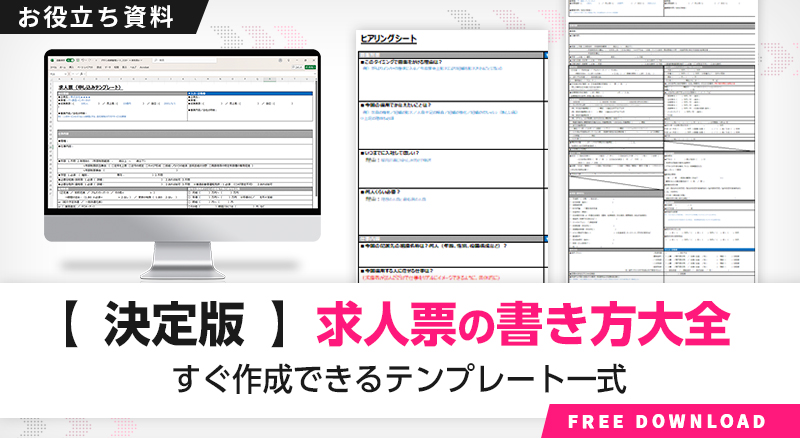よくある「あの言葉」で応募率が下がる!?転職希望者に応募を躊躇させる「NGワード」を解説
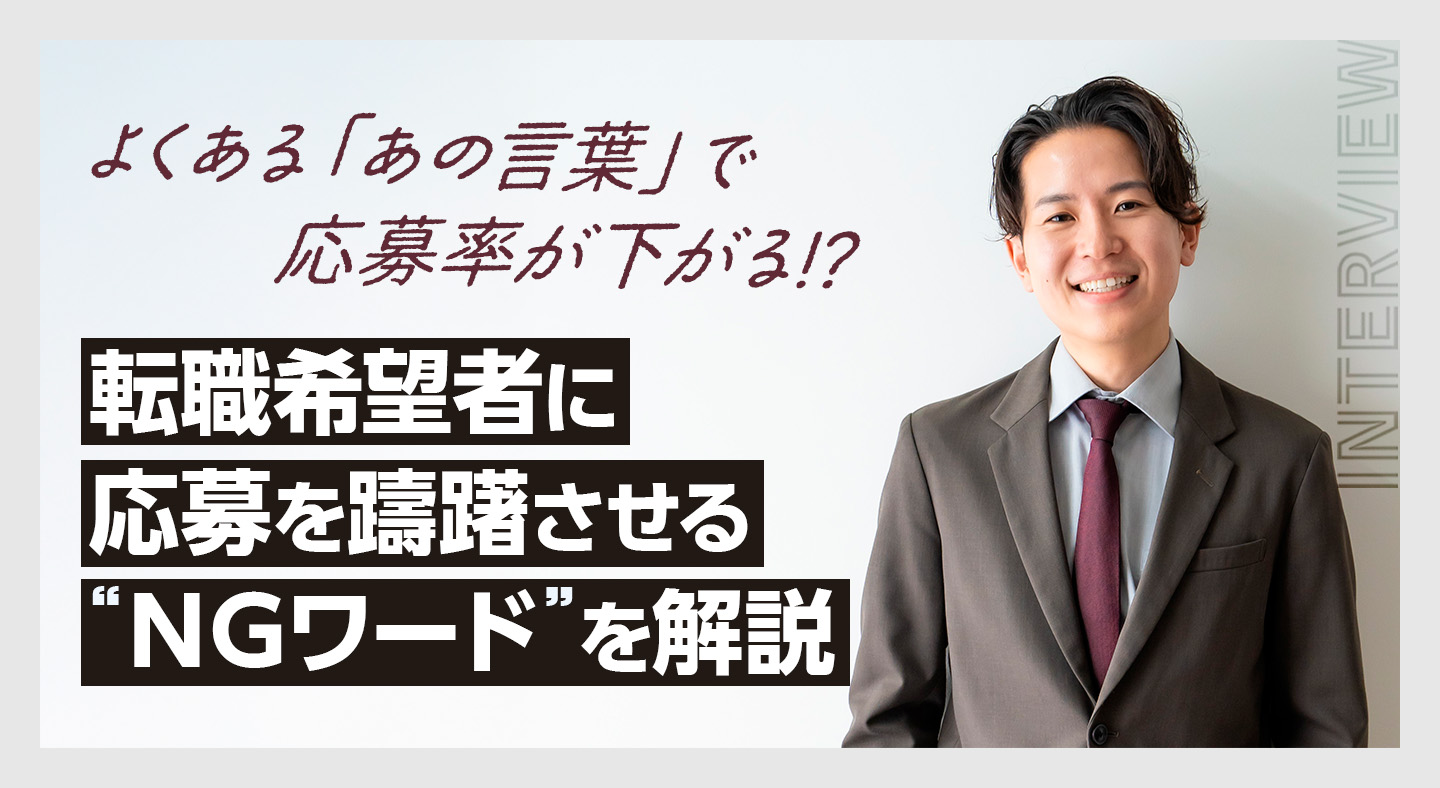
-
企業にとってのわかりやすさと、転職希望者にとってのわかりやすさは違う。転職希望者が求人票に求めているのは具体性を伴う「みずみずしい表現」
-
当たり前に使っている「社内用語」や、高頻度で使われる「未経験歓迎」「若手から活躍」などのコピーも、転職希望者が応募をためらう要因に
-
転職希望者の心理を知るために人材紹介サービス担当者などの第三者チェックを入れる。中途入社したばかりの人や入社受諾済みの人の意見など、自社内にもヒントが多数
良かれと思って求人票に記載している言葉が、実は転職希望者の気持ちを萎えさせてしまっているとしたら?
採用難が続く中、「とにかく自社への応募を増やしたい!」と考えている人事・採用担当者は多いでしょう。人材紹介サービスや求人広告、ダイレクト・ソーシングなど、さまざまな手法を活用しているにも関わらずなかなか応募率が上がらない…。その背景には、転職希望者に応募を躊躇させる「NGワード」があるのかもしれません。
転職希望者の心を捉え、応募率を高めていくには、どんな表現を意識すべきなのでしょうか。数多くの企業で人事コンサルティングや面接を手がける株式会社人材研究所の安藤健氏に、転職希望者の心理を聞きました。
企業と転職希望者の「わかりやすさ」は違う
企業への応募を検討する際に、転職希望者はどんな情報を重視しているのでしょうか。
安藤氏:転職希望者が見ているポイントは、「働きがいがあるかどうか」だと感じます。
働きがいとは「働きやすさ+やりがい」。働きやすさについては、自社に安心して働ける就労条件や環境が整っていることを伝える必要があります。やりがいは目に見えにくいものなので、やる気を高める職場風土や仕事自体の面白さをわかりやすく伝えるべきでしょう。
私が企業の採用活動を支援する際に重視しているのは、こうした働きがいに関する情報を“乾いた”表現ではなく、“みずみずしい”表現で求人票などに記載することです。

写真提供:株式会社人材研究所
「みずみずしい表現」とは。
安藤氏:企業にとってのわかりやすさと、転職希望者にとってのわかりやすさは異なります。転職希望者が求める情報を伝えるために必要なのが、“みずみずしい”表現なんです。
企業にとってのわかりやすさは、短く簡潔に表現されているもの。つまり“乾いた”表現になっているものです。実際の求人票を見ていると、企業にとってのわかりやすさで表現され、転職希望者にとっては分かりづらくなっていると感じることが多いです。
転職希望者にとってのわかりやすさは、自分自身がその仕事をしているイメージが湧くもの。必ずしも簡潔にまとめなくても構いません。文章が長くなることを厭わず、職場環境や風土、仕事の面白さなどを表現するべきだと思います。転職希望者向けの情報発信で写真や動画が多用されるのも、“みずみずしい”表現で伝えることが重視されているからですよね。
その「社内用語」や「職種名」は伝わっていないかも?
転職希望者に自社の働きがいを伝える際、逆に転職希望者が応募をためらってしまうような「NG表現」があれば知りたいです。
安藤氏:前述のように、転職希望者の心理を踏まえることなく、企業にとってのわかりやすさが優先されている求人票ではNG表現を見かけることが多いです。まずは言葉の使い方に関する部分で、いくつか例を挙げましょう。
■業界や自社特有の専門用語
業界未経験者向けに業界や自社特有の専門用語を使ってしまうと、当然ながら言葉の意味自体が伝わらない可能性があります。
求める人材を経験者に限定し、あえて業界用語を使うねらいがあるなら別。たとえば人事経験者を採用したい場合に「母集団形成」という言葉を使ってスクリーニングするのはアリだと思いますが、未経験者向けならば「自社への応募者を集めること」など、わかりやすく伝えるべきです。
■社内でしか通じない用語
文化人類学では、未開のジャングルなどで先住民族の調査をする際に、彼らの身内でしか使われていない言葉を「ジャーゴン」といいます。企業においても、内輪のみで使われすぎてジャーゴンになっている言葉があるんです。
特に福利厚生や制度を説明するときには、自社特有の名称をそのまま伝えてしまいがちですね。私が知る企業ではリフレッシュ休暇を異なる名称にして使用していますが、社内用語のまま伝えても転職希望者は理解しづらいでしょう。
■企業によって意味の異なる多義的な言葉
これは職種名で発生しがちです。たとえば「住宅コンサルティング営業」と一口に言っても、会社によって任される役割は違うはず。ヒアリングから受注、プラン提案、納品、アフターフォローまで一貫して携わる会社もあれば、納品以降はカスタマーサクセスが担っている会社もあるでしょう。
職種名はとかく誤解を生みがちです。私が知る某メーカーでは、一つの商材に特化している営業を社内で「ハイプロ営業」と呼んでいるのですが、転職希望者からは「超ハイレベルな営業」だと思われてしまうこともあります。求人票で表現する際には適切に言い換えることが大切です。

写真提供:株式会社人材研究所
「未経験歓迎」「若手が活躍」などの定番コピーが逆効果に?
安藤氏:続けて、求人票や求人広告でキャッチコピー的に使われる「ありがちな表現」によって、転職希望者が応募をためらってしまう可能性も見ていきましょう。
■「アットホーム」「風通しの良い」などのあいまいな表現
これらはあまりにも頻繁に使われている表現なので、そもそも他社との差別化になりません。転職希望者によっては、「わざわざこんなことを書くなんて、本当はアットホームじゃないのでは?」と勘ぐってしまう可能性もあります。
誤解されることなく明確に伝えたいのであれば、「当社のアットホームとは」を“みずみずしく”説明することが必要でしょう。たとえば「当社では階層にかかわらず、役職ではなく○○さんと名前で呼んでいる」「会議では上下関係なく『それって本気で言っていますか?』という発言が飛び出すなど、率直な議論をしている」といった情報です。
ここで意識すべきなのは、場合によっては自社のデメリットになるかもしれない情報も濁さずに伝える「RJP」(リアリスティック・ジョブ・プレビュー)の考え方です。極端に伝えすぎると母集団形成の段階で失敗することもありますが、求人票の内容が抽象的すぎてRJPの要素がまったくないと、転職希望者にスルーされてしまう可能性が高いのです。
■「急募」「未経験歓迎」などの定番コピー
これらも非常によく使われる言葉ですね。
「急募」と書かれた求人情報を見た転職希望者の中には、「そんなに社員が辞めているんだ…」と不安になる人がいるかもしれません。事業拡大や新部署設立など急募理由がポジティブなら、それを具体的に詳しく説明するべきです。
「未経験歓迎」と書かれていると、「未経験でもいいけど、本当は経験者がほしいのかな…」と不安になってしまう転職希望者もいます。経験者サイドからしても、「未経験歓迎ということは、自分の経験を最大限に活かすのは難しいのかも」と警戒してしまうかもしれません。
もし経験者も未経験者も本当に歓迎しているなら、求人票を完全に分けたほうがいいですね。そもそも未経験可の求人は提示される給与幅が広くなりがちで、経験者にとっては魅力が薄れます。経験者限定なら「年収600から800万円」で提示できるのに、未経験も可としていることで「年収400から800万円」といった提示になる。これをやってしまっている企業は多いはずです。未経験者向けと経験者向けで求人票を分けてしまえば、双方に魅力的な打ち出しができるでしょう。
■「若手のうちから活躍できる!」
これはポジティブな意味合いで求人票に載せている企業が大半ではないでしょうか。
しかし、本当に成長志向やキャリアアップ志向のある若手人材には「若いうちから活躍できるということは、どこかでキャリアが頭打ちになってしまうのでは」と思われたり、「若手に責任だけを押しつける余裕のない会社なのでは」と勘ぐられたりすることもあります。
なぜ若手のうちから活躍できるのか。その先にはどんなキャリアの可能性があるのか。できることなら実際に活躍しているハイパフォーマーへのインタビュー内容なども紹介し、“みずみずしく”情報を伝えたいところです。
転職市場で自社が採用に成功するための「3つの条件」
NG表現の例を聞き、良かれと思って書いていることが実際にはどう伝わっているのか、転職希望者の心理を理解することが本当に重要なのだと感じました。
安藤氏:そうですね。私は、今の転職市場で採用に成功するためには3つの条件が求められると考えています。
・自社の魅力や強みを言語化できていること
・選ぶのではなく、自分たちが選ばれる立場だと理解して振る舞えていること
・転職希望者目線に徹底的に立っていること
言われてみれば「その通り」と感じる人が多いと思うのですが、実際の採用活動では実践できていない企業がとても多いのも事実です。上記のような視点は営業部門やマーケティング部門などでは重視されていますが、同じ企業内でも、人事にそのノウハウが行き渡っていないケースをよく目にします。
営業やマーケティングから人事へのジョブローテーションがあるところはうまく実践できていると思います。でも、人事の仕事が管理的で、上から下りてきた採用目標をこなすことに精一杯になっている企業ではなかなか実践できません。だからこそ3つの条件を強く意識していただきたいと思っています。
転職希望者の心理に近づける方法があれば教えてください。
安藤氏:お勧めしたいのは、人材紹介サービス担当者などの第三者に「自社の求人票にわかりづらい表現がないか」を見てもらうことです。業界内や社内でしか通じない用語があれば指摘してもらえるでしょうし、プロの目から見て「ここはもっと具体的な情報がほしい」といったアドバイスも得られるはずです。
さらに身近な方法としては、中途入社したばかりの人や入社受諾済みの人など、自社の常識に染まり切っていない人に見てもらうのもいいですね。人事の目線では気付けなかった表現の落とし穴が明らかになるかもしれません。転職希望者の心理を知るヒントは、身近なところにたくさんあるんです。
取材後記
安藤さんが指摘するNG表現の例を聞きながら、求人票作成に慣れていくことには弊害もあるのかも…と感じました。「未経験歓迎」「若手から活躍」といった表現を見て、安心感を抱いたり、応募意欲を高めたりする転職希望者もいるでしょう。しかし誰しもが同じように受け止めるわけではありません。過去にはうまくいった表現であっても、現在のリアルな転職希望者心理を探りながら、新しい目で見直しを続けていくべきではないでしょうか。
企画・編集/森田大樹(d’s JOURNAL編集部)、野村英之(プレスラボ)、取材・文/多田慎介
<決定版>求人票の書き方大全【すぐ作成できるテンプレート一式】
資料をダウンロード